| |
| ”新美南吉 ” と ”ごんぎつね” |
| |
 南吉の作品は全部でいくつあるのでしょうか~? 南吉の作品は全部でいくつあるのでしょうか~? |
|
童話123編、小説57編、童謡332編、詩223編、俳句452句、短歌331首、戯曲14編、
随筆等17編とされています。題名しかわかっていない作品や、
同じ作品の遺稿などもあって、分類の仕方により、数は変わってくるようです。。 |
|
|
 南吉はどんな童話を書いたのでしょう~? 南吉はどんな童話を書いたのでしょう~? |
|
南吉の童話は、物語性が豊かだといわれています。
物語が展開するストーリーの面白さがあるということでしょうか。
作品の多くがふるさとの岩滑を舞台にし、岩滑の方言や習慣を採り入れながら
書かれていることも大きな特徴です。
また、子どもが大人になっていく過程を心の内側から丁寧に描いた作品も注目されています。 |
| |
 南吉はどんな詩や童謡を書いたのでしょう~? 南吉はどんな詩や童謡を書いたのでしょう~? |
|
南吉は一口では言いきれない色々の詩を書きました。内容により大きく分けてみましょう。
❖ 明るくさわやかな作品
❖ はかなく美しい作品
❖ つらく悲しい作品
❖ ユーモアとペーソスに富んだ作品
❖ その他の作品
どれも南吉文学に特徴的なものといえます。
ただ、南吉はあまり大げさな詩や童謡はつくらなかったそうです。 |
|
 南吉の童話で一番人気のある作品はなんでしょう~? 南吉の童話で一番人気のある作品はなんでしょう~? |
|
やはり「ごんぎつね」だと思います。
でも、「手ぶくろを買いに」が好きな人も「ごんぎつね」に負けないくらいいます。
「久助君の話」のような子どもの心理を描いた作品も注目されてきています。
❖ ちなみに~このサイトの管理人は「手袋を買いに」が大好きです。 |
|
 南吉本人が気に入っていた作品はなんでしょう~? 南吉本人が気に入っていた作品はなんでしょう~? |
|
どれも南吉にとって大切な作品だったと思います。
そのなかでも「久助君の話」は初めての童話集のタイトルにしようと
考えていましたので、特に思い入れがあったのかもしれません。 |
|
 どうしてキツネがよく出てくるのでしょう~? どうしてキツネがよく出てくるのでしょう~? |
|
キツネが持つ神秘的なイメージとコギツネのかわいらしさを愛したのでしょう。
南吉童話には、キツネ以外にも、牛や犬、デンデンムシもよく登場します。
南吉は動物園に行かないと見られないような動物はあまり描かず、
身近にいる動物を好んで物語に登場させました。
また、南吉は民話からストーリーの面白さを学ぼうとしていました。
民話にはキツネが魅力的なキャラクターとしてよく登場しますから、
その影響もあったのではないかと思われます。 |
|
 "ごん" は本当にいたのでしょうか~? "ごん" は本当にいたのでしょうか~? |
|
"ごん" は南吉が考え出した物語の中のキツネです。
しかし、岩滑には六蔵狐(ろくぞうぎつね)と呼ばれ、村人から親しまれていた
キツネがいました。六蔵狐に弁当を分けてやった村人が畑にタバコ入れを忘れたら、
六蔵狐が届けてくれたという話も伝わっています。
南吉が「ごん狐」を書くとき、六蔵狐のことを思い浮かべることがあったかもしれません。 |
|
 "兵十" は本当にいたのですか~? "兵十" は本当にいたのですか~? |
|
"兵十" は南吉が考え出した物語の中の人物です。
しかし、岩滑新田の江端兵重(えばたひょうじゅう)という人が、
はりきり網で魚を捕ったり、鉄砲で鳥などを撃つことが好きだったので、
この人がモデルになったのではないかと考えられています。 |
|
 「ごんぎつね」はいつから教科書に載っているのでしょう~? 「ごんぎつね」はいつから教科書に載っているのでしょう~? |
|
昭和31年に大日本図書という出版社が初めて4年生の国語科教科書に採用しました。
それからだんだん採用する出版社が増え、
昭和55年からはすべての教科書に載るようになりました。 |
|
 どうして "ごんぎつね" という名前になったのですか~? どうして "ごんぎつね" という名前になったのですか~? |
|
はっきりはわかりませんが、岩滑の北にある権現山(ごんげんやま)から
とったのではないかと考えられてます。その理由は、南吉がノートに書いた
下書きの原稿が「権狐」で同じ漢字を使っていること、権現山の辺りには
南吉が小学生の頃まで実際にキツネが住んでいたことなどがあげられます。
また、「手に負えないいたずらっ子」「腕白小僧」という意味で「権太」(ごんた)
という言葉がありますので、「いたずらぎつね」という意味がこめられているかもしれません。 |
 |
| |
|
童話「ごんぎつね」の里山、権現山は五郷社(古くは権現社)の鎮守の森として、
今なお豊かな自然を残し、その景観は見る者に安らぎを与えます。
ここは新美南吉の童話「ごんぎつね」の舞台になったと言われ、
その昔はキツネも多く生息していました。
近年でも、この森で野生のキツネが撮影されています。 |
| |
 「ごんぎつね」に出てくる "中山さま" ってどんな人ですか~? 「ごんぎつね」に出てくる "中山さま" ってどんな人ですか~? |
|
戦国時代、中山勝時という武将が岩滑を治めていました。
勝時は徳川家康の母である於大の妹を妻にしていたので、家康の叔父にあたります。
昭和の初め、その子孫が岩滑に戻ってきて、南吉の家の近くに住んでいました。
南吉は中山家によく出入りし、昔の鉄砲やよろいを見せてもらったり、
この地方の民話を聞いたりしていました。 |
| |
 「ごんぎつね」に出てくる "はりきり網" ってどんな網ですか~? 「ごんぎつね」に出てくる "はりきり網" ってどんな網ですか~? |
|
大雨が降った後に池から落ちてくるウナギを川の下流で捕るための網です。
普通は待ち網といいますが、川幅いっぱいに「はりきって」使うため、
岩滑では "はりきり網" と呼んでいました。 |
 |
| |
 「ごんぎつね」に出てくる "おはぐろ" ってなんでしょう~? 「ごんぎつね」に出てくる "おはぐろ" ってなんでしょう~? |
|
結婚した女性が歯を黒く染める習慣で、
「ごんぎつね」が書かれた昭和の初め頃には、まだしている人がいました。 |
|
 「ごんぎつね」に出てくる "赤い井戸" ってどんな井戸~? 「ごんぎつね」に出てくる "赤い井戸" ってどんな井戸~? |
|
半田市の隣の、常滑市で焼かれる土管を利用した井戸です。
素焼きに近く赤っぽい色をしていて、江戸時代から作られていました。
大正時代に入ると黒い釉薬(ゆうやく)のかかった立派なものが流行りましたが、
すべてが黒いものに変わったわけではなく、赤いものも使われ続けました。 |
 |
|
 「ごんぎつね」に出てくる "おねんぶつ" ってなんでしょう~? 「ごんぎつね」に出てくる "おねんぶつ" ってなんでしょう~? |
|
亡くなった人の一周忌や三周忌などの年忌に、親戚や付き合いのあった人が集まり、
お坊さんと一緒に仏壇の前でお経や念仏を唱えることです。
終わった後、お茶を飲んだり、食事をしたりしました。 |
|
 外国でも南吉の童話は読まれているのでしょうか~? 外国でも南吉の童話は読まれているのでしょうか~? |
|
画家の黒井健さんによる絵本『ごんぎつね』(偕成社)が
フランスと中国で出版されているほか、
同じ黒井健さんの絵本『手袋を買いに』(偕成社)がフランス、アメリカ、中国、韓国で
出版されています。また、最近は中国で南吉の童話集や絵本が次々に出版されています。 |
|
|
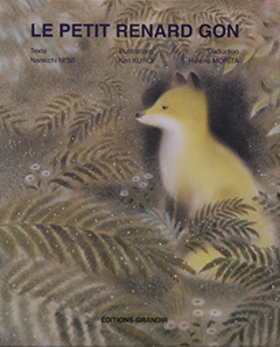 |
| 「ごんぎつね」フランス語・・・挿絵・黒井 健 |