|
切手の豆知識 その1 (最初の切手、切手の呼名、切手の種類)
最初の切手
日本で最初の切手が発行されたのは、明治4(1871)年3月1日です。 当時は旧暦なので、3月1日は現在の4月20日に当たります。
切手の図案は、当時の紙幣と同じく「竜」で、額面が江戸時代からの貨幣単位である「文」であるため「竜文切手」と呼ばれています。
種類は、48文、100文、200文、500文の4種類で、1シート40枚で構成されていました。
当初、郵便料金は宛地制であり、最低料金が100文でした。 48文は重量超過の割増料金用に使われていました。 48文は半端な金額のようですが、当時、
一般的に96文で100文となる九六勘定(2、3、4のいずれでも割り切れるという計算上の都合からできたものといわれています)が使われており、この九
六勘定から考えると100文の半分ということになります。
竜文切手の製造は、大蔵省印刷局の前身である紙幣寮が設立されていなかったため、太政官札など紙幣製造を明治2年から請け負っていた京都の銅版師松田敦
朝(玄々堂)に委託されました。 印刷方法は銅凹版(エッチング)で、当時はまだ原版を複製する技術がなく1シートの原版は一枚一枚を手彫りにしたので、同
じ額面の中でも、細かく観察すると、切手ごとに微妙な差異がみられます。
切手の呼名
日本の近代郵便制度の創始者である前島密(まえじま ひそか)が、この切手という言葉を当てたといわれています。 お金を払って得た権利を証明する紙片の
ことを、日本では古くから 切手と呼んでいました。 切符手形(きりふてがた)という言葉を短くし切手と呼んでいたのです。 切手という言葉は、当時の人々にはとても馴染み深い言葉であったようです。 切手と呼んでいました。 切符手形(きりふてがた)という言葉を短くし切手と呼んでいたのです。 切手という言葉は、当時の人々にはとても馴染み深い言葉であったようです。
ちなみに、郵便制度確立に尽力した前島密は、1円切手に描かれています。
切手の種類
通常郵便切手と記念・特殊切手
日本国で発行した、あるいは発行している「通常郵便切手」の種類はたくさんあります。 同じ図柄の切手を、別の時期の発行切手に使っているものもあります
が、色彩や表記など多少の改訂がされています。 額面によって発行枚数は異なりますが、本来の郵便事業のために発行されているもので、図柄の改訂が行われるまでは常に製造されており、いつでも郵便局で購入することができます。



同じ図柄の例
単色刷りで表記変更(左)、 多色刷りで色彩変更(中)、 単色刷りから多色刷りへ(右)
それに対して「記念・特殊切手」は本来の郵便料金前納証明という役割に加え国内外への風物紹介や行事の記念などのPR媒体として発行されています。 通常
切手が数億 枚発行されるのに対し記念切手は1,000万枚から3,000万枚程度の発行です。 郵便切手コレクターのために発行する切手と言えるかもしれま
せん。 枚発行されるのに対し記念切手は1,000万枚から3,000万枚程度の発行です。 郵便切手コレクターのために発行する切手と言えるかもしれま
せん。
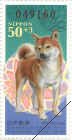
年賀切手も記念・特殊切手に含まれます。 昭和10年(昭和11年用)から発行されており、昭和34年(昭和35年用)から干支に因んだ図柄が採用され、
(昭和46、47、48、49年発行は干支とは異なる図柄)現在に至っています。 戦後1,000万枚程度の発行だったのが現在では8,000万枚以上発行
されています。
平成18年の年賀切手(左)と中部国際空港開港記念切手(右)
|