 沖縄最初の夕食 石垣島ホテルにて |
沖縄最初の日(1/28)は石垣島の、ビーチホテルサンシャイン,、海が見える場所での夕食であった。夕食は色々な料理が出たが、豚の角煮が一段と美味しかった。魚は熱帯魚を食べているようで、一つ何処か味が違い、私の舌にはあわなかった。 |
|||||||
| ビーチホテルサンシャインは、海と空の碧さに彩られた楽園の島で石垣島にある 。真っ白なビーチの先に竹富島、西表島が一望できる絶好のロケーションであった。 泳いだ後は、「海辺のテラス」(屋外レストラン)で喉の渇きを癒すこともできる。快適な場所であったが、流石、1月では泳いでいる人もいなかった。 |
 石垣島のホテルの朝食 後ろは浜辺 |
|||||||
石垣島のホテルの朝食 後は浜辺 |
同じ場所で義弟夫婦も朝食後の記念撮影した。 食堂の直ぐ前は、芝生一面が貼りめぐされ、直ぐ横には、泳いだ後は、「海辺のテラス」で喉を潤うことも出来る配置になっていた。夏季では非常に楽しい時間を費やすことが出来るであろう。 |
|||||||
| ホテル内の庭 及び 近くを散歩すると、流石ここは南国、色々な植物、花が、あちことに咲いていた。これはホテルの庭に咲いていた花の一つである。 ホテルには、3階に露天風呂付展望大浴場があり、ここからの パノラマビュー(サンセット ビュ ー)は一段と美しい。 |
ホテルの前に咲いていた南洋の花 |
|||||||
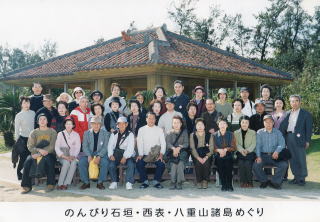 |
沖縄旅行に一緒に行ったメンバー 合同記念写真 | |||||||
| 沖縄には各所に綺麗な花が咲いていた |  |
|||||||
海辺で戯れる昔の乙女 |
海は広い、という言葉の通り、本当に広い。竹富島を前に望み、綺麗な海がどこまでもどこまでも遠くに続いていた。そんな美しい名所を朝の散歩で、綺麗な海辺に入り、子供心に戻って戯れているのは、義弟の妻である。 | |||||||
| 義弟夫婦の浜辺での記念撮影をした。この世に二人しかいない錯覚におちいる場所であった。 夏の時期ならば、人々で多くの海水浴が来る場所である。 |
義弟夫婦 |
|||||||
わが夫婦 |
我々夫婦も同じく、この広い海岸で記念撮影をした。 このように広い場所で写真を撮ると、なんと人間は小さいものかと痛感した。 |
|||||||
| ビーチホテルサンシャインのホテル内の庭は南国風にアレンジされ、その前で記念撮影をした。 この庭には、色々な南国の花が、1月というのに咲いていた。 |
||||||||
石垣港 |
2日目は(1/29)は近くの港、石垣港より西表島の大原港に船で渡り、ジャングルクルーズを楽しんだ。仲間川は浦内川に次いで西表島で2番目に大きい川である。 西表島(いりおもてじま)の中央部、南よりの山地から東に流れ、仲間港にそそぐ二級河川で、浦内川につぐ大きな川で、河口付近の川幅は200mを越えるところもある。水量はそれほど豊富ではないが、沿岸には広大なマングローブ湿地帯が形成されていて、多様な水辺の生物を育んでいる。 |
|||||||
| 西表島の仲間川ジャングルクルーズでマングローブの林を抜けていくと、最大級のサキシマスオウの木がある。右の写真はその下で記念写真を撮った妻である。 この木は推定樹齢 350年、樹高18m、板根地際の周囲がなんと35.1m、板根の高さは最大3.1mもあり、西表島にある同樹種の中でも群を抜いて大きく、その存在感と威風には圧倒されてしまう。 サキシマスオウノキ(先島蘇芳木)はマングローブ背後の湿地林に生育するアオギリ科の常緑高木で、アフリカ東岸から東南アジア、ポリネシアにわたる広い範囲に分布し、日本では奄美大島以南の南西諸島に見られる。 |
サキシマスオウの木の下で |
|||||||
サキシマスオウの木の下で |
サキシマスオウの木を含め、多くの木々が、流域のマングローブを構成、生息していた。見たこともない実をつけた木もあった。 ここ、西表島だけにイリオモテヤマネコが生息している。  イリオモテヤマネコは、世界中で西表島のみに生息している一属一種の野生のネコで、1965年に発見され、1967年の動物学会に発表されて今世紀最大の発見とまでいわれた。本種は原始的なネコの特徴をそなえているといわれ、その体型は頭、胴は長く、尾は太くて身近く、大きさはイエネコよりやや大きめ、現在生息頭数は100頭前後と推定されている。 |
|||||||
| 流域のマングローブ林は国内最大の規模を誇り、中流にサキシマスオウノキがあり遊覧ボートで行った。 近くでは日本最大のサキシマスオウノキも見られるほか、満潮時には上流8kmほどの所まで船でさかのぼれるため、亜熱帯の珍しい動植物をまじかに見ることができる川の一つとなっている。 |
、仲間川 |
|||||||
マングローブの若木 |
マングローブ(Mangrove)とは熱帯、亜熱帯地方河口汽水域の塩性湿地に生育する森林のことで、紅樹林とも言う。 マングローブ林を構成する植物は世界で70〜100種程度あり、主要な樹木の多くはオヒルギ、ヤマヤマヒルギ、ハマザクロ、ヒルギダマシ、ヒルギダモドキ、ニッパヤシ等がある。 左の木々はこれからマングローブを構成する若木である。 マングローブ林は海水の影響のもとにある。海側は干潟に接し、陸側は海水の影響がなくなるところまでにあたる。主要な動物は海産動物である。潮が引いた時には、多数の蟹が出現する。干潟の近くではオマネキ類やミナミコメツキガニなどが出現し、森の中にはアシハラガニ類やイワガニ類が多数生息している。潮が満ちると地面に掘った穴の中にもぐりこんでやり過ごすものが多いが、中には木に登って過ごすものもある。なお、潮が満ちるとガザミやノコギリガザミなど、大型のカニが姿を現す |
|||||||
| 西表島で食事を取った。 豚の角煮は美味しかったが、それに加えて、沖縄の名物、ゴーヤで作った各種の料理が珍味で美味しかった。 右の写真は食事を取った場所の庭園での記念写真である。 |
庭園 |
|||||||
西表島と由布島を水牛車で行く |
西表島と由布島をつなぐ浅瀬を水牛車でのんびり渡ることがこの地の名物である。由布島は島全体が亜熱帯植物園となっており、色々な植物を楽しむことが出来た。 由布島は、周囲2.15km、海抜1.5mの小さな島で、4万本近くのヤシ類を中心に亜熱帯の樹木や花々が生い茂っている。島は、約4万坪の広さ、島全体が砂によってできている。東側はビーチが発達し、西側は、西表までつづく浅瀬にマングローブが繁る。西表島へつながる海は、遠浅で、満潮でも1mほどしかない。 |
|||||||
| 由布島は、動植物の宝庫、熱帯亜熱帯の生き物たちが、自然のまま生息している。海岸には、マングローブが広がり、トントンミー(とびはぜ)やシオマネキなど無数の生き物を見ることができる。天然記念物のセマルハコガメや珍しい蝶に野鳥そして、鮮やかな花々など、亜熱帯の自然がそのまま豊かに息づいている。 由布島は、かつて竹富島や黒島から移り住んだ人々が対岸の西表島に水田を作って暮らしていた。その頃、農耕用に使われたのが、”水牛”、この優しくて利口な動物は昔も今も島の人と共に生きている。 |
水牛車で安里ユンタの響きを聞きながら |
|||||||
 |
1971年の台風で大きな被害を受けほとんどの人が、西表島へ移ったが、現在の園長”西表正治”おじいは、島に残りパラダイスガーデンのロマンを描きながらヤシを植え花を育て手づくりの楽園を作りあげた。 由布島の現在の人口は5戸、15人である。 亜熱帯の樹木や花々が咲く中で、妻と義弟の妻の記念写真である。 |
|||||||
| 由布島の綺麗な花の下で記念撮影をした。 |
わが夫婦 |
|||||||
義弟夫妻 |
由布島の重要な観光資源となっている水牛車の水牛は、もともと台湾から連れて来られた雄の「大五郎」と雌の「花子」のひとつがいの水牛が繁殖して現在に至ると云われている。 水牛は水牛車を引くために2歳からトレーニングを始め、3歳頃から本格的に車を引っ張るようになる。飼い主以外の人が水牛を触ることは禁じられてはいるが、非常におとなしく、飼い主の言う事をよく聞く。その従順な姿と賢さに驚いたり感動したりする観光客が多い。我々も水牛に触ったり、乗ったりして楽しんだ。 |
|||||||
|
かつての由布島は、竹富島や黒島から移り住んできた人々で栄えていたが、1969(昭和44年)の台風により島は壊滅的なダメージを受けてしまい、ほとんどの島民は亡くなってしまった。これをきっかけに西表島などに移り住んでいってしまった。 島の人々が消えていく中で、西表正治おじい夫婦は島に残り、再び島に人々が戻ってくることを信じてたくさんのやしの木や花を植え続けていった。そうして現在では、沖縄本島では見ることが出来ない熱帯性の植物がたくさん生い茂り、数々の動物たちが生息している |
義弟夫婦 |
|||||||
我々夫婦 |
由布島には西表正治おじい夫婦が植え、大切に育てた色々な大きな木々があった。その前で、何回か記念写真を撮った。 |
|||||||
| その西表の正治おじい夫婦が育んできた木々には、各所に「由布島」と木の名前が書いてある名札があった。その前でも記念撮影を撮った。 | 名札の前で |
|||||||
| 特に、目に付くのはハイビスカスが綺麗であった。 | ||||||||
 水牛車の列、 おじいの安里ユンタが聞こえてくる。のどかな風景であった。 |
水牛車の前で義弟夫妻 |
|||||||
海を渡る水牛車 |
水牛車 美原の出発所で水牛車に乗る。帰りも同じく、水牛車にゆられるのはなんともオツなもの。この水牛、人が歩くよりゆっくり歩いているよう。急に止まったかと思えば、おしっこをしたり、ウンコしたりして、風情がある。水牛の歩く方向が、ちょっとずれてきてるなぁと思いきや、最後は方向修正して、ちゃんとたどり着く。 帰りはおじいが安里ユンタを引いてくれ、なんともスローでのんびりとしたもの。美原の出発所からも安里ユンタの響き渡る音が聞こえてくる。 |
|||||||
| 2日目のホテルは,室内には2つの寝室と、リビングルームそして台所があり、知り合いの人の複数家族が長期滞在できるような設計になっていた。 4人一部屋で一夜を過ごした。 そのホテルの裏には大きな木が生えていた広場があった。又、前側は海岸になっており、散歩を兼ねて、この辺りを散策した。 |
||||||||
浜辺で遊ぶ、3人 |
このホテルの前の海岸も、白浜が遠くまで続いていた。しかしこの海岸には砂ばかりではなく多くの貝殻があった。 3人が貝殻を拾い戯れていた。 |
|||||||
| 2日目(1/29)の食事は、八重山の伝統芸能が楽しめるレストランで過ごした。きらびやかな衣装と優雅な舞踊からは南国のゆっくりとした時の流れを感じられる。 レストラン「あじ彩」で八重山舞踊を楽しみながら夕食を取った) |
演者を囲んで一行4人 |
|||||||
八重山踊りの一節 |
石垣島郷土、八重山踊りである。 |
|||||||
| レストラン「あじ彩」で八重山舞踊を見ながら、夕食を楽しんだ。 優雅に舞う伝統の八重山舞踏を見ながら、伊勢海老を中心に地元素材を贅沢に使用した彩り豊かな山海の幸を賞味した。 石垣島初のレストランシアターであった。 |
||||||||
義弟の舞台参加 中央の男性が義弟である。。 |
義弟は踊りが好きで、お客参加の合図がでたら、真っ先に舞台に上がり、即興で八重山舞踊を踊り、楽しんでいた。 |
|||||||
| 兎に角、沖縄の木々は大きい。ホテルの裏のグランドで、どれほど大きいか、二人の妻君が両手を広げて、気の大きさを測っていた。 | 木が大きい |
|||||||
竹富島に渡る |
3日目(1/30)は石垣島から竹富島に渡り、竹富島(集落内)を水牛車で観光 そして、マイクロバスで星砂の浜等の観光した。 竹富島(たけとみじま)は沖縄県の八重山諸島にある島で、沖縄県八重山郡八重山町に属している。八重山の中心地である。 島の中央部にある集落全体が、木造赤瓦の民家と白砂を敷詰めた道という沖縄古来の姿を保っている。なお、「竹富」は近代になってからの当て字で、明治半ばまでは「武富」と表記されることが多く、かつてはタキドゥンと呼ばれていた。現在も住民には「テードゥン」と呼ばれることが多いという。 |
|||||||
| 島の集落をのんびりゆっくり巡る水牛車は、竹富島観光の名物である。ガイドさんの名調子に耳を傾けながら、昔ながらの風情を残す町並みを30〜40分かけてまわるので、竹富島を知るには良い観光である。 ガイドのおじいの名調子にのって、狭い石垣に囲まれた白い道を上手く、ゆっくりゆっくり水牛車は進んで行く。 右の写真は ゆっくり歩く水牛車に乗り、ガイドに説明を受けて、集落内を見学している写真であるが、驚いたことに、水牛の鳴き声は、普通の牛の「もー」と違い、「ヘー」となくには吃驚した。 |
ゆっくり進む水牛車 |
|||||||
石垣の敷地 |
沖縄本島から南西に450kmの八重山諸島、石垣島の南西に点在する大小16の島からなる。 最大の島は県下でも2番目に大きい西表島である。。 また、日本最南端の有人島波照間島・竹富島・小浜島・黒島・鳩間島・新城島・嘉弥真島の島々からなり、東シナ海と太平洋に翡翠玉のようにちらばる。 |
|||||||
| 現在の竹富島の人口は300名余り。年寄りがほとんどの島だけど、年がら年中観光客がやってくるのはなぜかね」などと、ガイドの愉快な島解説が続く。 右の写真は集落内で一番古いものだと言う。 | 島内最古の家 |
|||||||
白砂の道路 |
途中、沖縄民謡「安里屋ユンタ」の主人公、安里屋クヤマの生家の前を通 りかかると、ガイドが三線を爪弾きながら自慢のノドを披露。 「この島が安里屋ユンタの発祥の地なんですよ」と解説をはさみながら、もう一曲。ゆらゆら牛車に揺られるのんびり観光は時間を忘れさせてくれる。 舌の写真が安里屋クヤマの生誕の地である。 |
|||||||
| 竹富島の有名な民謡「安里屋ユンタ」に唄われた伝説の美は、 沖縄の代表的な民謡「安里屋ユンタ」に歌われた美女クヤマの生まれた家。「安里屋ユンタ」には、苛酷な人頭税の時代に横暴な役人の求愛を拒んだ、彼女の気丈さが歌われている。 また、家を取り囲む美しい石垣は、クヤマが芋を掘った帰りに石を一個ずつ持ち帰り、それを積み上げて出来たと伝えられている。 |
美女クヤマの生誕の地 |
|||||||
水牛に乗り記念撮影 |
女クヤマはここで生また。現在も子孫の方が暮らしている。 サァ 安里屋(あさどや)ぬ くやまによ サァユイユイあん美(ちゅ)らさ うん生(ま)りばしよ マタ ハーリヌチンダラ カヌシャマヨ サァ 目差主(みざししゅ)ぬ 請(く)ゆだらよ サァユイユイあたろ親(や)ぬ 望(ぬず)むたよマタ ハーリヌ チンダラ カヌシャマヨサァ 目差主や 我(ば)なんばよ サァユイユイあたろ親(や)や 此(く)りゃおいすよ マタ ハーリヌ チンダラ カヌシャマヨ 左の写真は、安里屋ユンタを聞き、説明を聞き、帰ってきた後、記念に水牛に乗りパチリ。 |
|||||||
| 自由時間を利用して、近くを散歩した。どこもが、石で造られた垣根と赤瓦の屋根、そして、屋根の上には魔よけの作り物があった。 一軒の家の前で記念撮影をした。 | 民家の前で |
|||||||
戻ってきた水牛車 |
集落内を歩いていると、帰ってくる水牛車とよくであった。水牛は大人しく、一緒に写真を取らしてくれた。これがそのうちの1枚である。 | |||||||
| 水牛車の集まる、売店の横に珍しい花々を見つけた。名前は分からないが、その中の一つである。 | ハイビスカス |
|||||||
義弟夫妻、星砂があったかな? |
星砂の浜は、中野集落と住吉集落の中間にある砂浜で、丁度由布島のまったくの反対側に位置する。 名の通り海浜の砂には星砂が含まれている。星砂は大形の有孔虫である”バキュロジプシナ”というサンゴの一種で、その遺骸が推積して砂浜となったのである。海中では藻に付着し、黒い色をした生きているバキュロジプシナを見ることができる。 実際星砂は乱獲されてしまい、ほとんど見つけることができなく、その代わりにおみやげ屋さんえ買わないと手に入らないかもしれない。 |
|||||||
| 川平湾 石垣島の北西部にある川平湾(かびらわん)はエメラルド色のサンゴ礁の海に緑をたたえた小島が浮かぶ景勝地。その美しさは全国で8ケ所しかない国指定名勝地に選ばれる。石垣島で1番の景勝地で日本百景にも選ばれている。 湾内には小さな島が点在し、季節、天候によって変化する海の色とで、美しい風景を作り出している。 |
海底の珊瑚と魚 |
|||||||
白浜の上で記念撮影 |
しかし、船底がガラス張りのグラスボートでみると、色鮮やかな熱帯魚と珊瑚礁を観察することが出来る。只、残念なことは海底に空き缶等が沈んでおり、景観を損ねていた。 遊泳は禁止されているが、グラスボートで遊覧しながら、美しいサンゴ礁が楽しめる。太陽光の具合によって様々に変化する透明度の高い海とそれを囲む緑が織り成すパノラマはまさに絶景であった。また、世界初の黒真珠養殖に成功した場所としても有名である。 その素晴らしい白浜で記念撮影をした。 |
|||||||
付近の素晴らしい風景に踊りたくなるような雰囲気をかもし出していた。踊っているは私の家内。 |
白浜で踊る |
|||||||
唐人墓の前で |
唐人墓 1852年に、アメリカに渡航中の中国人労働者が、船員からの虐待に耐えかね石垣島に下船した。その後、派遣された英国軍により処刑された128人を祀る墓である。 悲惨な過去の出来事ですが、墓は龍や船、神様などカラフルで明るい印象の墓である。 |
|||||||
| 1852年中国アモイから400人の労働者がカリフォルニアへ送られる途中、その過酷な仕打ちに蜂起、石垣島に380人が下船した。後にイギリス兵の追っ手や病気、自殺等で亡くなった128人を祀るために建てられたお墓である。 景色のよい場所に立ち中国風の極彩色の装飾が見事。このすぐそばに観音崎灯台があり、展望台から見る夕日は絶品です |
||||||||
見事な木の下で |
唐人墓付近の広場には、写真のような珍しい根っこを持った大きな木があった。その大きな木の下で記念撮影をする女二人であった。 | |||||||
我々男共も同じように木の下で記念撮影をした。下の写真は石垣島の空中写真である。 |
||||||||
軒下の知らぬ花 |
最後のショッピング店の軒下に珍しい木?花?を見つけて写真を取った。 ここを最後に石垣空港に行き、ローカルの小さな飛行機であったが、ジェットエンジン付きの飛行機で、那覇空港に飛んだ。 |
沖縄の石垣島、西表島 由布島 八重山諸島巡りの思い出を纏めてみた。のんびり石垣・西表、八重山諸島めぐりの団体旅行を義弟にあたる稲垣夫妻と参加した。時期は2004年01月28日〜30日の寒い時期であったが、流石沖縄は北緯25度付近で、快適な,2泊3日の旅程であった。
成田空港よりジャンボで飛立ち、那覇空港 -経由でローカル飛行機により石垣空港についた。今回の旅行は沖縄本土を避け、自然が一杯の石垣島、西表島、由布島、そして竹富島を訪ねた。
-経由でローカル飛行機により石垣空港についた。今回の旅行は沖縄本土を避け、自然が一杯の石垣島、西表島、由布島、そして竹富島を訪ねた。