| 元旦 |
『 元日や こがねの鞍に 馬白し 』 |
|
|
 |
元日だなぁ。黄金の鞍に馬の毛の色が白く映えている。 |
|
|
 |
元日に飾られた白い馬なので、神社に奉納された神馬を見たと思われる句です。
新年から縁起の良いものを見られた喜びが伝わってきます。 |
|
| 春 |
『 病僧の 庭はく 梅 の さかり哉 』 |
|
|
 |
病に伏せていた僧が掃いている庭では、梅の花が盛りをむかえていることだ。 |
|
|
 |
病と梅の花のさかりを対比させている句です。春が近づいて体調の良くなって
きた僧侶が、リハビリのように体を動かしている様子を詠んでいます。 |
|
|
『 箱鳥 や 明はなれ行く 二子山 』 |
|
|
 |
箱鳥が飛んでいるなぁ。二子山は夜がすっかり明けている。 |
|
|
 |
「箱鳥」とは顔鳥の別称ですが、顔鳥がどんな鳥を指しているのかは
わかっていません。一説によるとカッコウのことだとも言われています。 |
|
|
『 春 に我 乞食やめても つくしかな 』 |
|
|
 |
春に私は土筆を取って生活するような乞食をやめて筑紫に行くことができる。 |
|
|
 |
「つくし」に「土筆」と「筑紫」が掛かっています。
この句が詠まれたのは作者が幕府の仕事で筑紫国に赴くことが決まった時で、
それまで貧しい暮らしをしていたためこのような句が生まれています。 |
|
|
|
 |
|
|
『 春の夜 は たれか初瀬の 堂籠(どうごもり) 』 |
|
|
 |
春の夜に誰かが初瀬の長谷寺に籠っている。 |
|
|
 |
「初瀬」とは奈良県桜井市にある地名で、西国三十三番の長谷寺がある
ことで有名です。『枕草子』や『源氏物語』にも登場するため、
初瀬という地名だけで通じるようになっています。 |
|
|
『 大峯や よしのの奥の 花 の果(はて) 』 |
|
|
 |
大峯山の麓を歩いてきたなぁ。桜で有名な吉野の山の桜ももう山奥にしか
咲いていない。初夏が近づいて桜の花は果てまできてしまった。 |
|
|
 |
吉野は桜の名所ですが、場所によって開花時期が変わってきます。
一番奥地では2週間ほど遅くなるため、奥地にいけばまだ桜は咲いていますが、
近づく初夏を「花の果て」という表現で表しているのが面白い句です。 |
|
| 夏 |
『 湯殿山 銭ふむ道の 泪(なみだ)かな 』 |
|
|
 |
本殿のない湯殿山を祀る神社には多くのお賽銭が落ちている。
そんな道を、お賽銭を踏みながら歩くとありがたさに涙が出てくることだ。 |
|
|
 |
「湯殿山」は山形県にある出羽三山の1つで、山岳修行の山です。
神社の本殿がないため、人々は思い思いの場所にお賽銭を捧げていたのです。 |
|
|
『 卯の花 を かざしに関の 晴着かな 』 |
|
|
 |
卯の花を髪飾りにして関所跡を通る晴れ着にしよう。 |
|
|
 |
この句が詠まれたのは、『奥の細道』での白河の関跡です。白河の関は
昔から東北地方への入口とされていて、多くの歌や文学作品に登場する
名所でした。関所を通る時は衣服を改めると言われていましたが、旅装以外は
持ち合わせていないので、せめて花を髪飾りにして装おうとしている句です。 |
|
|
|
 |
|
|
『 剃り捨てて 黒髪山に 衣更 』 |
|
|
 |
旅を始める前に黒髪を剃り捨てて、黒髪山の麓で衣替えの日をむかえたことだ。 |
|
|
 |
「黒髪山」とは日光の「男体山」のことで、和歌ではしばしば「黒髪山」と
呼ばれます。この句は『奥の細道』の出発前に詠まれた旅への決意の句で、
作者は僧形となって芭蕉の旅に随行しました。 |
|
|
『 卯の花 や 兼房見ゆる 白毛かな 』 |
|
|
 |
白い卯の花だなぁ。白髪を振り乱して戦ったという増尾兼房を
思い起こさせるような白毛であることだ。 |
|
|
 |
「増尾兼房」とは義経伝説に登場する武将で、老齢ながら最期まで義経に従い
戦ったと言われています。卯の花の白と、この時訪れていた
義経最期の地である平泉を合わせて、老武将の姿を偲んでいる句です。 |
|
|
『 波こえぬ 契ありてや みさごの巣 』 |
|
|
 |
「波がこえない」という約束があるかのような絶壁に巣作りしているなぁ、
このミサゴの巣は。 |
|
|
 |
この句は百人一首にも収録されている
「契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは」という歌が
もとのようです。末の松山のように、決して波がこえないとわかっているから
あんなところに巣を作るのだろうか、という感嘆が見て取れます。 |
|
| 秋 |
『 行き行きて 倒れ伏すとも 萩 の原 』 |
|
|
 |
行けるところまで旅をして、倒れ伏しても萩の咲く野原であれば本望だ。 |
|
|
 |
曾良は『奥の細道』の旅に同行していましたが、体調を崩したことにより
芭蕉と別れる事になります。この句はその時に詠まれた句で、例え体調を崩して
倒れたとしてもそこが萩の花の咲く野原であれば良いという覚悟を示した一句です。 |
|
|
|
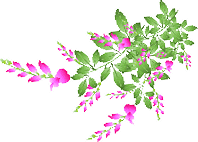 |
|
|
『 かさねとは 八重撫子の 名なるべし 』 |
|
|
 |
かさねという名前は、八重撫子の名前に違いない。 |
|
|
 |
この句は『奥の細道』の旅の途中で、道案内として馬を貸してくれた家の
子供たちの1人の名前を聞いて作者が詠んだ句です。「かさね」という名前から、
八重咲きに花びらが重なる八重撫子の姿を連想したのでしょう。 |
|
|
『 三日月 や 影ほのかなる 抜菜汁 』 |
|
|
 |
三日月が出ているなぁ。月の光はほのかで、抜菜汁を食べながら見よう。 |
|
|
 |
この句は同じく芭蕉の弟子の各務支考の「三日月日記」に出てきます。
「抜菜汁」も「間引菜」という季語と同じ意味ですが、
三日月を題材に詠む句会での一句のため、季語は三日月になります。 |
|
|
『 終宵(よもすがら) 秋風 聞くや うらの山 』 |
|
|
 |
一晩中強い秋の風が裏山に吹くのを聞いていたことだ。 |
|
|
 |
体調を崩して『奥の細道』の旅から離脱した作者が詠んだ句です。
病のため、師の芭蕉と別れ、一人この寺に泊まったが、寝つかれない。
裏の山を秋の風が颯々と吹く音を一晩中聞いていたことだ。
1日違いで芭蕉も同じ寺に宿泊していますが、
お互い一人旅となったことで、より一層寂しさが増しています。 |
|
|
『 くるしさも 茶にはかつへぬ 盆 の旅 』 |
|
|
 |
山道を歩く苦しい巡礼の旅でも、巡礼者をもてなす人達のおかげで
お茶には困らない盂蘭盆会の旅であることだ。 |
|
|
 |
この句は熊野詣での際に詠まれています。盂蘭盆会の時期は巡礼者をもてなす
サービスがあったようで、山道でも喉が渇くことはなかったと
当時の様子がよく描写されている句です。 |
|
| 冬 |
『 畳(たたみ)めは 我が手のあとぞ 紙衾 』 |
|
|
 |
その畳みめは私がたたんだ手のあとだよ、師である芭蕉の身につけていた紙衾は。 |
|
|
 |
紙衾とは紙でできた防寒具のことで、『奥の細道』で芭蕉が使っていたものです。
その紙衾をもらった同門の友人へ、からかいも含んで投げかけた句です。 |
|
|
『 一つ戸や 雀はたらく 冬がまへ 』 |
|
|
 |
ただ一つの我が家の扉よ。雀が働いているように動いている冬支度だ。 |
|
|
 |
「冬がまへ」とは風よけや雪よけを家の周囲に施して冬に備えることです。
雀がせっせと玄関前で動いている様子を、
まるで冬構えを施しているようだと見守っています。 |
|
|
|
 |
|
|
『 むつかしき 拍子も見えず 里神楽 』 |
|
|
 |
難しい拍子も見えない里の神楽だ。 |
|
|
 |
作者は有名な神道家に神道を習っており、神楽などの習俗に関しては
よく知っていました。里の神楽は複雑な表紙もなく、
単純かつシンプルだからこそ力強いと鑑賞している一句です。 |
|
| 大晦日 |
『 侘しさや 大晦日の 油売り 』 |
|
|
 |
侘しいことだ。大晦日になっても油売りがやってくる。 |
|
|
 |
大晦日という年の瀬でも働いている油売りを見ての一句です。
当時の灯りは油が燃料だったため、年末年始でも油は必ず必要になる物資でした。 |
|
![]()