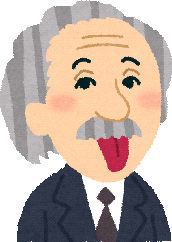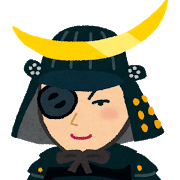|
||||||||||||||||||||||||
| 松島について | ||||||||||||||||||||||||
| 松島は宮城県松島町・松島湾内に位置し、大小260以上もある島が 複雑にいりくんだ「絶景」で知られています。 京都の天橋立や広島の宮島とともに、「日本三景」の一つに数えられるほど、 国内でも有数の名勝地です。陸地から臨む雄大な海には、いくつもの島が点在し、 日本らしい風情豊かな景色が広がります。 また、松島には他の顔があり、「信仰の場」でもあります。 松島群島の中にある「雄島(おしま)」は、昔から多くのお坊さんや修験者が訪れて 修行に明け暮れています。「奥州の高野」とも呼ばれています。 「高野」とは、真言密教を日本に広めた空海(弘法大師)が修行場として 開山した聖地『高野山』のことです。 松島に訪れた時には、「聖地」としての風に触れてみてはいかがでしょうか。 ※ 東日本大震災で一部が崩壊や変形した島もあります ※ |
||||||||||||||||||||||||
| 俳句 | ||||||||||||||||||||||||
| 俳句は五・七・五の十七音から成る世界最短の定型詩で、日本が誇る伝統芸能の一つです。 限られた文字数の中で、人々の心情や情景を伝えるという広がりを持った表現が俳句の魅力 といえます。そんな数ある名句の中でも特に有名な「松島やああ松島や松島や」という句、 一度はみなさんも耳にしたことがあるのではないでしょうか? 繰り返し詠まれる松島とはどのような場所なのか、 またこの句を詠んだ作者についても気になります。 「松島や・・・」は、松尾芭蕉の「おくの細道」の「松島・元禄二年五月九日・十日」 の条に収められているます。 |
||||||||||||||||||||||||
| 意味 | ||||||||||||||||||||||||
| こちらの句は現代語訳すると、 「松島という場所はなんと表現したらよいのだろうか・・・本当に松島は・・・」 という意味になります。 松島というあまりの絶景を前に、作者の言葉が出てこない様子が感じとれます。 |
||||||||||||||||||||||||
| 季語 | ||||||||||||||||||||||||
| こちら句には俳句の基本ともいえる季語が含まれていません。 このように季語や季節感を持たない俳句のことを「無季俳句」と呼びます。 実は季語の有無については、俳句が盛んであった江戸時代から議論されている問題でした。 松尾芭蕉の門人・向井去来は著書『去来抄』の中で、 「先師曰く、発句も四季のみならず、恋、旅、離別等、無季の句もありたきものなり」 (芭蕉は、恋、旅、離別などを詠む場合は、無季の句があってもよいのではないかといった) と述べています。事実、松尾芭蕉もいくつかの無季俳句を残しており、 「歩行ならば 杖つき坂を 落馬かな」などがあります。 |
||||||||||||||||||||||||
| 場所は現在の何県でしょう | ||||||||||||||||||||||||
| この句に詠まれている松島とは、一体どんな場所だったのでしょうか。 松島は、宮城県の松島湾内外にある大小260余りの諸島の総称です。 また、それら諸島と松島湾周囲を囲む松島丘陵も含めて呼ぶこともあります。 松島は古くは平安時代に歌枕の地として知られていましたが、松尾芭蕉の『奥の細道』の 中で紹介されてからは、全国的にその名が広まり文人墨客を中心に多くの人々が訪れました。 さらに松島は月の名所としても知られており、相対性理論を発表した アルベルト・アインシュタインも月見をするためにわざわざ松島をまで訪れ、 名月を楽しんだといわれています。 この松島という地には、世界的物理学者 ” アインシュタイン ” や、芭蕉による リスペクトやまない ” 西行法師 ” など、歴史的偉人とのつながりは多く残っているのです。 |
||||||||||||||||||||||||
| ” アインシュタイン ” と松島 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理学者アルベルト・アインシュタイン(1879~1955年)が来日してから100年以上になります。 アインシュタインが日本滞在で最も感動した景色は、松島の湾内に浮かぶ月だったそうです。 古来、幾多の文人墨客を魅了してきた「松島の月」。多忙なスケジュールのアインシュタインが 目にすることができたのは、観光地のインフラが整ったばかりというタイミングのおかげだったのです。 当時の記事によると、アインシュタインは1922年12月2日、東京・上野駅から東北線で仙台駅に到着。 夜にもかかわらず、駅は受け入れを主導した東北帝大(現東北大)の教員や学生らで埋め尽くされ ました。アインシュタインがホームに降りると、「万歳」と叫び熱烈に出迎えたそうです。 アインシュタインは、翌3日午前10時から、仙台市公会堂で約3時間半講演した後、 東北線に乗り込み旧松島駅で降りました。同駅から松島海岸地区の五大堂を結んでいたのが、 宮城初の電車である「松島電車」で、その電車に乗って午後4時すぎに、やっと松島海岸に着きました。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 自然の景色を丸ごと 味わいつくす感性は、繊細で豊かに受け継がれてきたものです。 松島には、観月亭があり、松島湾の景色を四季折々楽しむために作られました。 夕暮れ時に、湾の島々が紅に染まりながら、刻々と影絵になってくれてゆくのを、 感動と共に見つめ、 やがて現れる美しい月を待っていたのでしょう。 空の月は、静かな海に写りこみ、一服の絵が完成されます。 松島の海に写る月を見るために、アインシュタインは松島を訪れたのだそうです。 月の美しさを、一番綺麗に見える場所として松島を選んだとすると、感動します。 感性は磨かれて育つものです。日本人として生まれて、 既に持っているものはあっても、育んでいかないと育たないものもあります。 注意力や、観察力を高めながら、感性を育てたいものです。 美しいもの、面白いものを見るとき、脳は快感を体験します。 脳は快適な状態を好みますので、たくさん感動体験をして、 脳を刺激しましょう。 |
||||||||||||||||||||||||
| ” 西行法師 ” と松島 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本三景・松島には、湾に浮かぶ島々を眺める絶景ポイントがいくつかあります。 代表的なのが、四大観(しだいかん)と称される「富山」「多聞山」「大高森」 「扇谷」の4つの展望地です。しかし、それらに勝るとも劣らないと 思われるのが、桜咲く季節の『西行戻しの松公園』です。 西行戻しの松公園は、JR仙石線・松島海岸駅の西側に位置する 姉取山の斜面中腹にあります。松島湾を箱庭のように一望できる ビュースポットです。松島湾を望むよう作られた公園には 260本余の桜(ソメイヨシノ・オオヤマザクラ)が植えられています。 桜が満開の時期に見ることができる松島湾を借景とした その光景は息をのむ美しさで、訪れた人は皆声をそろえて 「松島にこんな桜の名所があるとは知らなかった」とその絶景を 愛でています。園の名称は、平安時代の歌人・西行法師が この地を訪れた際に、松の大木の下で出会った童子と禅問答をして敗れ、 松島行きをあきらめたことに由来すると言われています。 西行と牧童との禅問答。その気になる内容は、公園内に設置された看板に書かれています。 |
||||||||||||||||||||||||
| 西行と牧童との禅問答 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 西行法師 | ||||||||||||||||||||||||
| 西行は法師は、平安時代から鎌倉時代初期にかけての歌人で、 かの松尾芭蕉も目標とした人物でした。 祖先は武家・藤原氏で、奥州平泉の藤原氏と同じです。 武芸達者で若いころは当時のエリート集団でした。 「北面の武士」に選ばれましたが、突然エリートコースの道を捨て出家しました。 高貴な身分の女性との色恋沙汰や、童子との禅問答に敗れた逸話など、 ユーモラスで、人間味溢れる言い伝えが数多く残されていて、 西行法師が庵を結んだとされる場所、子どもとの問答に負けて、 道を引き返したとされる「西行戻し」の言い伝えなどが、 日本全国に残されていて、日本人にもっとも親しまれている歌人の一人です。 東北地方には、出家してまもなく旅行で訪れていますが、 晩年にも東大寺再建の勧進のため、平泉を訪れています。 芭蕉の「奥の細道」は、西行法師が東北地方を訪れた時の足跡を 辿る旅だったと伝わっています。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 参考 :「松島や」の前に記された「おくの細道」の一節です | ||||||||||||||||||||||||
| 仰(そもそも) ことふりにけれど、松島は扶桑(ふさう)第一の好風(かうふう)にして、 凡(およそ)洞庭(どうてい)・西湖こを恥(はぢ)ず。 東南より海を入(いれ)て、江(え)の中(うち)三里、浙江(せっこう)の潮(うしほ)をたゝふ。 島々の数を尽して、欹(そばだつ)ものは天を指ゆびさし、ふすものは波に匍匐(はらばふ)。 あるは二重(ふたへ)にかさなり、三重(みへ)に畳(たた)みて、左にわかれ右につらなる。 負(お)へるあり抱(いだけ)るあり、児孫(じそん)愛するがごとし。 松の綠こまやかに、枝葉(しえふ)汐風(しほかぜ)に吹(ふき)たはめて、 屈曲(くっきょく)をのづからためたるがごとし。 其(その)気色(けしき)窅然(えうぜん)として、美人の顔(かんばせ)を粧(よそほ)ふ。 ちはや振(ぶる)神のむかし、大山(おほやま)ずみのなせるわざにや。 造化(ぞうくわ)の天工(てんこう)、いづれの人か筆をふるひ詞(ことば)を尽(つく)さむ 。 雄島(をじま)が磯は地つゞきて海に出(いで)たる島也。 雲居禅師(うんこぜんじ)の別室の跡、坐禅石(ざぜんせき)など有(あり)。 将(はた)、松の木陰(こかげ)に世をいとふ人も稀々(まれ)見え侍りて、 落葉(おちば)・松笠(まつかさ)など打(うち)けふりたる草の菴(いほり)閑(しずか)に 住(すみ)なし、いかなる人とはしらずながら、先(まづ)なつかしく立寄(たちよる)ほどに、 月(つき)海(うみ)にうつりて、昼のながめ又あらたむ。 江上(かうしゃう)に帰りて宿を求(もとむ)れば、窓をひらき二階を作(つくり)て、 風雲の中に旅寐(たびね)するこそ、あやしきまで妙(たへ)なる心地はせらるれ。 |
||||||||||||||||||||||||
| 「松島や・・・」の作者は松尾芭蕉ではなく「田原坊」では~? | ||||||||||||||||||||||||
| 松尾芭蕉が松島を訪れた際、「あまりの美しさに言葉が浮かばずこう詠むしかなかった」 という逸話が残されています。しかし、実際は芭蕉の句ではありません。 芭蕉の松島への憧れは強く、『奥の細道』の冒頭でも「松島の月先心にかゝりて」と述べ 旅を始めるほどでしたが、なぜかこの中では松島に関する俳句を残していませんでした。 どうやらその場で句が思い浮かばなかったのは事実のようで、句は詠んだものの 風光明媚な松島につりあうものができなかったともいわれています。 それでは本当の作者とは一体誰なのでしょうか? 近年の研究により、芭蕉の時代よりも下った江戸時代後期の 田原坊(たわらぼう)の作ではないかとされています。 「田原坊」… 江戸後期の狂歌師。 「狂歌」 … 和歌の細かい作法を取り払い字数だけ合わせて自由に詠う。 桜田周甫の記した『松島図誌』(当時の観光ガイドブックのような冊子)用に 詠んだ句で、元句は『松嶋や さて松嶋や 松嶋や』が収められています。 当時は松島の宣伝用のキャッチコピーとしてつくられたものでしたが、「さて」を 「ああ」に変えられ、芭蕉が詠んだ句として広まってしまったのが真相のようです。 同書には、「芭蕉が松島の絶景に圧倒され句を詠めなかった」というエピソードも 掲載されたため、この句の作者が松尾芭蕉だと混同して今に伝えられたのかもしれません。 こちらの句には、ほかの有名俳句と比較したとき季語はおろか切れ字や比喩法など、 俳句らしい表現技法は使われていません。ただ、そういった表現技法を用いていないからこそ、 普段俳句に親しみが無い人でも広く受け入れられたのではないしょうか。 もしくは、松島の絶景は四季折々いつでも美しいということを伝えたかったのかもしれません。 当時の世の人々は、言葉を失ってしまうほどの松島の素晴らしい眺めとは一体どんなものなのか、 興味をかきたてられたのでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||
| 芭蕉の弟子「曾良」、松島についての句 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 松島と伊達正宗と五郎八姫 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 瑞雲峰天麟院について | ||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| 「天麟院」(てんりんいん)は松島の国宝寺院『瑞巌寺』の並びにあり、国重文寺院『円通院』に 隣接する仙台藩主・伊達家ゆかりの寺院であり、伊達政宗の長女・伊達五郎八姫の菩提寺。 境内は無料で拝観できます。 五郎八姫は伊達政宗と正室・愛姫との間に生まれた長女であり、弟には正宗の後を継いで 二代目仙台藩主となった伊達忠宗が、そして異母兄には宇和島藩初代藩主・伊達秀宗が居ます。 五郎八姫自身は徳川家康の六男で高田藩主の松平忠輝に嫁いだものの、忠輝が高田藩主を改易に なったことをきっかけに仙台へ戻り出家。 政宗は愛娘に同情して、信仰生活を全面的に支援した――のだとか。 天麟院は姫の菩提寺で、境内にある五郎八姫御霊廟は、円通院三慧殿、陽徳院などと並び 松島の三霊廟とも言われるそうです。 本堂の横にこじんまりとした池泉庭園があります。五郎八姫は晩年茶の湯をたしなまれ、 それに伴った井戸や築山、池苑の存在が案内板には書記述があります。 この池泉庭園がそれであるとは書かれていないのですが、“200年以上も経た名木”という ドウダンツツジの姿がこの池泉の周辺に見られるので、この池泉もその当時からの遺構なのでは と思われます。池の頭上にあるモミジとの組合せが紅葉時期にはきれいでしょうね。 |
||||||||||||||||||||||||
| 『島々や千々に砕けて夏の海』 | ||||||||||||||||||||||||
  |
||||||||||||||||||||||||
| 瑞巌寺 | ||||||||||||||||||||||||
| 仙台を出た松尾芭蕉と河合曽良は一路塩釜、松島へ。 道中、多賀城の「壺碑(つぼのいしぶみ)」をはじめ歌枕や塩釜神社を巡り、船で松島に渡った。 「おくのほそ道」冒頭で「松島の月先心にかゝりて」と記していた念願の地だ。 曽良の「日記」によると、到着は1689(元禄2)年5月9日の昼ごろ。 快晴だったと伝わっています。 |
||||||||||||||||||||||||
| ❖ 260余りの島々からなる松島 | ||||||||||||||||||||||||
|
日本三景の一つに数えられ、古くから歌枕、瑞巌寺を擁する霊場として知られていました。 芭蕉以前には伊勢出身の俳人「大淀三千風(みちかぜ)」が訪問しています。 三千風が1682(天和2)年に出版した「松島眺望集」は芭蕉の句を「桃青」の号で収録。 眺望集が松島行を促したとの説もあるようです。 |
||||||||||||||||||||||||
| ❖ 伊達家ゆかりの菩提寺 瑞巌寺 | ||||||||||||||||||||||||
|
天長5年(828年)に慈覚大師(じかくだいし)によって創建され、慶長14年(1609年)に |
||||||||||||||||||||||||
| 日本三景の一つ、松島にあり、山号を含めた詳名は 松島青龍山瑞巌円福禅寺(しょうとうせいりゅうざん ずいがんえんぷくぜんじ)。 平安時代の創建で、宗派と寺号は天台宗延福寺、臨済宗建長寺派円福寺、 現在の臨済宗妙心寺派瑞巌寺と変遷しました。古くは松島寺とも通称されていました。 江戸時代前期の元禄2年(1689年)に俳人松尾芭蕉が参詣したことにちなみ、 毎年11月第2日曜日には芭蕉祭が行われています。 また、大晦日には火防鎮護祈祷である「火鈴巡行」と一般も撞ける除夜の鐘が有名です。 |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
境内には、「臥龍梅」と呼ばれる紅白二本の梅の木があり、伊達政宗の手植えと伝えられています。 また、参道にはシンボルとも言える杉並木がりましたが、平成23年(2011年)3月11日の 東日本大震災の津波に見舞われ、その後の塩害によって立ち枯れが目立ったことから、 約300本が伐採されることになってしまいました。 同じ東北地方にある平泉の中尊寺と毛越寺、山形立石寺と共に「四寺廻廊」という 巡礼コースを構成しています。 |
||||||||||||||||||||||||
| 雄島 | ||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| 渡月橋と雄島 | ||||||||||||||||||||||||
  |
||||||||||||||||||||||||
| 朱塗りの渡月橋を渡ると、108の岩窟があったといわれる雄島(現在は50程度)。 その昔、死者の浄土往生を祈念した石の塔婆である板碑、 岩窟の中には五輪塔や壁面に法名の彫られたものが多く、まさに霊地です。 橋を渡り道を左に曲がって短いトンネルをくぐると、三方に岩窟のある崖と、 わずかばかりの平地があります。ここは見仏上人が、法華経60,000部を読誦した見仏堂の跡で、 奥の院といわれた場所。現在でも薄暗く、見仏上人は、この場所で12年間もの長きにわたって 修行を続けました。 また、江戸後期のころ、江戸からの便船が暴風に巻き込まれ、乗り合わせていた白キツネに 救われた話をもとに、 海難防止の守り神・新右衛門稲荷が祀られています。 渡月橋は東日本大震災の津波で流されてしまい、松島観光が再開した後もしばらく雄島は 立入禁止でした。2013年7月、ようやく新しい橋が架けられました。 |
||||||||||||||||||||||||
| ❖ 頼賢の碑 全島が霊場のようなこの島には句碑が多く、南端に国の重要文化財指定の頼賢の碑が 六角形の鞘堂の中に納められています。 高さ3メートルの碑の表面には、雷文と唐草文が ほどこされ、梵字と、右に「奥州御島妙覚庵」、 左に「頼賢庵主行實銘並序」と記してあります。 本文は、頼賢の徳をたたえたもので、松島の昔の様子も刻まれています。(国重要文化財) ❖ 松吟庵跡 松吟庵は瑞巌寺大103世通玄法達のために、その兄が頼賢の住んでいた妙覚庵の跡に建てたもので、 洞水和尚の詩にちなんで名づけられた伝えられています。 ここを訪れた芭蕉は「雲居禅師の別室の跡、座禅石など有。はた、松の木陰に世をいとふ人も まれまれ見え侍りて、 落穂松笠など打ちけぶりたる草の庵,閑にすみなし」と書いています。 この「草の庵」が松吟庵です。 ❖ 松尾芭蕉と河合曾良の句碑 雄島には、芭蕉の句碑と『おくの細道』に同行した曾良の句碑が建てられています。 芭蕉「朝よさを 誰まつしまぞ 片心」(桃舐集 元禄元年 1688年) 曾良「松島や 鶴に身をかれ ほととぎす」 |
||||||||||||||||||||||||
| 狂歌師流の諧謔 | ||||||||||||||||||||||||
| 『松島やああ松島や松島や』。松島湾を見渡し口ずさむ。 圧倒的な光景にただただ嘆息するばかりでした。 芭蕉の句と思われがちなこの歌。実は江戸後期の狂歌師田原坊の作で、 感嘆詞の「ああ」は元々「さて」だったそうです。 『島々や千々に砕けて夏の海』(蕉翁句集)。芭蕉は松島をこう詠みました。 「散在する島々。眼前に広がる夏の海に、美しく砕け散っているようだ」。 虚飾を排した写生のような一句。「ほそ道」の華美な記述とは対照的です。 人知を超えた自然の造形を前に、虚勢など意味をなさなかったのです。 陸海空が織りなす松島の眺望は、ありのままの人間を慈悲深く包み込んでくれているように、 すがすがしい表情で兜を脱ぐ俳聖の姿がそこにあったのでした。 |
||||||||||||||||||||||||