![]()
| |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| ❖ 漂泊・旅立ち (春) | ||||||||
| (季語はアンダーラインで示しています) | ||||||||
| 芭蕉庵を出発するときに詠んだ発句です。芭蕉はこの句を含んだ表八句を 懐紙にしたためて、江戸・深川の家の柱にかけて出立しました。 |
||||||||
| 草の戸も 住替る代ぞ ひなの家 | ||||||||
| 旅の第一歩として旅日記の一句目に記したものです。 | ||||||||
| 行春や 鳥啼魚(とりなきうお)の 目は泪(なみだ) | ||||||||
| ❖ 日光 (初夏) | ||||||||
| 詠んだ俳句のうち、「あらたうと」の句は、特によく知られています。 | ||||||||
| あらたうと 青葉若葉の 日の光 | ||||||||
| 剃(そり)捨(すて)て 黒髪山に 衣更 (ころもがえ) 河合曾良 | ||||||||
| 暫時(しばらく)は 瀧に籠るや 夏の初(げのはじめ) | ||||||||
| ❖ 那須野・黒羽・雲厳寺 (夏) | ||||||||
| 那須野・黒羽・雲厳寺で詠んだ俳句1句ずつです。 | ||||||||
| かさねとは 八重撫子(やえなでしこ)の 名成べし 河合曾良 | ||||||||
| 夏山に 足駄(あしだ)を拝む 首途哉 (かどでかな) | ||||||||
| 木啄(きつつき)も 庵(いお)はやぶらず 夏木立 (なつこだち) | ||||||||
| ❖ 殺生石・遊行柳・白河の関 (夏) | ||||||||
|
九尾の狐(玉藻の前)伝説の残る殺生石と西行の遊行柳(ゆぎょうやなぎ)に到着。 「白河の関」までが一つの関門だったらしく「ここまで来れた~」という気持ちが 「奥の細道」の紀行文から伝わります。 |
||||||||
| 野を横に 馬牽(うまひき)むけよ ほとゝぎす | 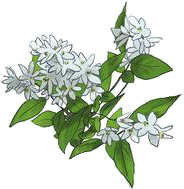 |
|||||||
| 田一枚 植て立去る 柳かな | ||||||||
| 「季語 : 田植え」 | ||||||||
| 卯の花を かざしに関の 晴着かな | ||||||||
| ≪河合曾良≫ |
||||||||
| 「殺生石」の伝説 | ||||||||
|
この地に伝わる「殺生石伝説」は、平安時代初めの鳥羽上皇の逸話です。 平安時代に、古代からインドや中国を荒らし回った妖狐「白面金毛九尾の狐」が、 とうとう日本へやって来ました。そして、妖狐は、「玉藻の前」という絶世の美女に 化身して、帝(鳥羽上皇)の寵愛を受けるようになったのです。 帝の命を奪い日本を意のままにしようとした「玉藻の前」は、陰陽師の阿部泰成によってその 正体を見破られ、本来の姿(九尾の狐)になって、「那須野が原」へ逃げ込んだのでした。 朝廷は、すぐさま上野介広常と三浦介義純に命じ、8万もの軍隊を派遣して「九尾の狐」を 退治させました。妖狐は射殺され、巨大な石となります。 そして、その怨念は毒気となって、それ以来、近づく人や鳥獣を殺し続けたのでした。 時はくだり、室町時代にこれを伝え聞いた名僧・源翁和尚が、この地を訪ねます。 そして、術をかけた杖をさして一喝すると、巨石はパッカーンと3つに割れました。 3つに分かれた石の1つは会津へ、1つは備後へと飛んで行き、残った1つがこの地に残り 「殺生石」として、今も語りつがれているのでした。 3つに割れて効力は薄まったかもしれませんが、「殺生石」の霊力はまだ残っています。 那須温泉神社の境内には、今も、妖狐の御魂を鎮めるため「九尾稲荷神社」が 祀られているのだそうです。 |
||||||||
| 芭蕉と曾良と「殺生石」 | ||||||||
| 松尾芭蕉と河合曾良は、大関藩の館代に一族を上げての大歓迎で迎えられます。 館代の弟が門人の桃翠(翠桃)だったというのもありますが、当時、すでに芭蕉が 俳諧師として大人気だったというのが、よく分かります。 そこで、芭蕉たちは、彼らから平家物語で有名な「那須与一」と縁のある神社や、 謡曲の題になった「殺生石」の話を、くわしく聞いたのです。芭蕉は源氏が大好きなので、 「那須与一」ゆかりの神社には、是非とも行きたかったでしょう。 帝の寵愛を受けた美女・玉藻の前に化けた九尾の狐が、退治されて変化したといわれる石にも 興味を持った彼らは、早速見に行くことにしました。 「殺生石」は、那須湯本温泉の近くにあり、付近には、今でも温泉地にありがちな 有毒ガス・硫化水素ガスが出ているのです。石から発生しているのではなく地下からですが、 昔は、今よりずっと強烈なガスが出ていたようです。そして、付近の地温は80〜90度と 高温で、発生する硫化水素ガスは空気より比重が重いので、 「殺生石」のような谷間の窪地にガスがたまりやすかったのでした。 昔の人は、それが有毒ガスによるものとは分からなかったので、 「妖狐の怨念」で石が霊力を持ったと考えていたと思われます。 |
||||||||
| ❖ 須賀川・朝積山・信夫の里 (夏) | ||||||||
| 風流の 初(はじめ)やおくの 田植うた | ||||||||
| 世の人の 見付ぬ花や 軒の栗 「季語 : 栗の花」 | ||||||||
| 早苗(さなえ)とる 手もとや昔 しのぶ摺(ずり) | ||||||||
| ❖ 飯塚の里・笠島・武隈の松 (夏) | ||||||||
| 笈(おい)も太刀も 五月にかざれ 帋幟(かみのぼり) | ||||||||
| 笠嶋は いづこさ月の ぬかり道 | ||||||||
| 桜より 松は二木を 三月越し | ||||||||
| 発句ではないので季語がなくてもいいそうです。 桜より三カ月後とあるので「夏」だとわかります。 |
||||||||
| ❖ 宮城野・松島 (夏) | ||||||||
| あやめ草 足に結ん 草鞋の緒(わらじのお) | ||||||||
| 松島や 鶴に身をかれ ほとゝぎす ≪河合曾良≫ | ||||||||
| ❖ 平泉 (夏) | ||||||||
| 「奥の細道」の俳句と言えばこの3句。どの句もとても有名です。 始めの2つは、芭蕉と曾良が同じ場所(平泉)で詠んだ俳句です。 芭蕉は、江戸・深川を出発してから44日目、5月13日に、奥州平泉を訪れ、夏草が生い茂る 荒野の風景を目の当たりにしました。 岩手県南西部に位置するこの地は、11世紀末から 12世紀にかけての約90年間、藤原清衡(きよひら)に始まる奥州藤原氏が、栄華を極めた 都市です。そして、兄・源頼朝に追われた義経が最期に身を寄せた場所でもあります。 俳句の前の散文で奥州藤原氏の滅亡に触れているので、 500年前のこの地であったことに想いをはせて詠んだとわかります。 この地に立って、芭蕉は、500年前に滅んだ藤原三代の栄華と源義経の最期に、 想いをはせて詠んだとわかります。 杜甫の名句「国破れて山河在り 城春にして草木深し」とつぶやき、 時を忘れて涙を流したと、『奥の細道』に記しています。 |
||||||||
| 夏草や 兵どもが 夢の跡 | ||||||||
| ❖ 意味 高館にのぼってあたりを見渡すと、藤原氏の栄華の痕跡はあとかたもなく、ただ夏草が茂る 風景が広がるばかりだ。(この夏草を眺めていると、すべてが夢と消えた儚さに心が誘われる) |
||||||||
| ここで同行者の ≪河合曾良≫ も句作しています。 義経主従が藤原泰衡の軍勢と戦ったとき、白髪を振り乱して、勇猛果敢に奮戦し壮絶な最期を 遂げた老臣・増尾兼房を想って詠ん詠んだ曾良の句です。 義経の老臣・兼房は、高館最期の日に、義経一家の最期を見届けた後、 館に火を放ち、敵の大将ともども火の中に飛び込み、壮絶な最期を遂げたと伝わります。 白い「卯の花」から「兼房の白髪」を連想して、当時に想いをはせて詠んだものです。 (兼房は架空の人物ともいわれます) |
||||||||
| 卯の花に 兼房(かねふさ)みゆる 白毛(しらが)かな ≪河合曾良≫ | ||||||||
| 続いて、芭蕉は平泉の中尊寺を訪れ、美しい金色堂を参詣しました。 この句も先のと同じく、移り変わる人の世と、時が流れても変わらず光り輝く「光堂」との 対比が、感じられます。松尾芭蕉は、この平泉に午前中3~4時間ほど滞在したと伝わっています。 『奥の細道』に記載されているのは、ほぼ史実どおりですが、経堂はこのとき実際は 閉じられていて、芭蕉は中を見ていません。経堂に「三将の像」があると記していますが、 実際にあるのは光堂です。これは、芭蕉が勘違いしたのではないかといわれています。 ちなみに、当時、金色堂(光堂)を保護していたのは、やはり仙台藩伊達家でした。 |
||||||||
|
||||||||
| ❖ 尿前(しとまえ)の関・尾花沢 (夏) | ||||||||
| 蚤虱(のみしらみ) 馬の尿(ばり)する 枕もと | ||||||||
| 涼しさを 我宿(わがやど)にして ねまる也 | ||||||||
| 這出よ(はいいでよ) かひやが下の ひきの声 | ||||||||
| まゆはきを 俤(おもかげ)にして 紅粉(べに)の花 | ||||||||
| 蚕飼(こがい)する 人は古代の すがた哉 ≪河合曾良≫ | ||||||||
| ❖ 石立寺・最上川 (夏) | ||||||||
| 山形県の石立寺と最上川で作ったこの2つの俳句も、よく知られた松尾芭蕉の代表作です。 |
||||||||
 |
||||||||
| 閑さや 岩にしみ入 蝉の声 | ||||||||
| 五月雨を あつめて早し 最上川 |
||||||||
| ❖ 出羽三山 (夏) | ||||||||
| 有難や 雪をかほらす 南谷 「季語 : 南薫」 | ||||||||
| 涼しさや ほの三か月の 羽黒山 | ||||||||
| 雲の峯 幾つ崩て 月の山 |
||||||||
| 語られぬ 湯殿にぬらす 袂(たもと)かな | ||||||||
| 湯殿山 銭ふむ道の 泪(なみだ)かな ≪河合曾良≫ | ||||||||
| ❖ 鶴岡・酒田 (夏) | ||||||||
| あつみ山や 吹浦(ふくうら)かけて 夕すゞみ | ||||||||
| 暑き日を 海にいれたり 最上川 | ||||||||
| ❖ 象潟(きさがた) (夏) | ||||||||
| 象潟(きさがた)や 雨に西施(せいし)が ねぶの花 | ||||||||
 |
||||||||
| 汐越(しおこし)や 鶴はぎぬれて 海涼し | ||||||||
| 象潟(きさがた)や 料理何くふ 神祭 ≪河合曾良≫ | ||||||||
| 蜑(あま)の家や 戸板を敷て 夕涼 | ||||||||
| ≪美濃国の商人・低耳(ていじ)作≫ | ||||||||
| 波こえぬ 契ありてや みさごの巣 ≪河合曾良≫ | ||||||||
| ❖ 越後路・市振(いちぶり) (秋) | ||||||||
| 文月や 六日も常の 夜(よ)には似ず | ||||||||
| 荒海や 佐渡によこたふ 天河 | ||||||||
| 一家(ひとつや)に 遊女もねたり 萩と月 | ||||||||
 |
||||||||
| ❖ 那古(なご)・金沢 (秋) | ||||||||
| わせの香(か)や 分入(わけいる)右は 有磯海(ありそうみ) | ||||||||
| 塚も動け 我泣声は 秋の風 | ||||||||
| 秋涼し 手毎(てごと)にむけや 瓜茄子(うりなすび) | ||||||||
| あかあかと 日は難面(つれなく)も あきの風 | ||||||||
| しほらしき 名や小松吹(ふく) 萩すゝき | ||||||||
| ❖ 小松・那谷寺(なたでら) (秋) | ||||||||
| 小松の多太神社を参詣し、「源平の争乱」で散った源氏の老武将・斎藤実盛を想って 詠んだ俳句です。松尾芭蕉は、源氏びいきで、特に木曽義仲に思い入れがありました。 「平家物語」でも有名なエピソード「実盛の最期」の聖地に立てて感動したのでしょうか。 |
||||||||
|
||||||||
| ❖ 山中温泉・全昌寺 (秋) | ||||||||
| 山中温泉で、同行していた弟子の河合曾良が体調を崩してしまいます。 曾良は旅を続けるのが困難になり、ここで芭蕉と別れ療養することになりました。 曾良の「行行て」の俳句にそのことが記されています。 |
||||||||
| 山中や 菊はたおらぬ 湯の匂 | ||||||||
| 行行て(ゆきゆきて) たふれ伏(ふす)とも 萩の原 ≪河合曾良≫ | ||||||||
| 今日(きょう)よりや 書付(かきつけ)消さん 笠の露 | ||||||||
| この句で、芭蕉は曾良の離脱を悲しんでいます。 「笠の露」にその気持ちが表れているのだそうです。 |
||||||||
| ❖ 全昌寺・汐越の松・天龍寺・永平寺 (秋) | ||||||||
| 終宵(よもすがら) 秋風聞(きく)や うらの山 | ||||||||
| 庭掃(にわはき)て 出(いで)ばや寺に 散柳(ちるやなぎ) | ||||||||
| 「季語 : 柳散る」 | ||||||||
| 物書て 扇引さく 余波哉(なごりかな) 「季語 : 扇置く」 | ||||||||
| ❖ 敦賀・色の浜 (秋) | ||||||||
| 月清し 遊行(ゆぎょう)のもてる 砂の上 | ||||||||
| 名月や 北国日和(ほくこくびより) 定(さだめ)なき | ||||||||
| 寂しさや 須磨にかちたる 濱(はま)の秋 | ||||||||
| 波の間や 小貝にまじる 萩の塵 | ||||||||
| ❖ 大垣 | ||||||||
| 蛤の ふたみにわかれ 行秋ぞ(ゆくあきぞ) | ||||||||
| 芭蕉は1689年(元禄2年)3月に江戸を出発し、東北の旅に出ました。 その旅の最後が、岐阜県「大垣」。「奥の細道」のゴールです。 3月から8月、約150日間もの長旅でした。 大垣の俳句も旅の最後の句ということで、よく知られています。 芭蕉がここに到着したとき、たくさんの弟子が先に来ていて芭蕉を迎え入れてくれたそうです。 体調不良で離脱した河合曾良も来ていて、ここで再開を果たせました。 |
||||||||
| 『奥の細道』の最後の句(結句)について | ||||||||
| 芭蕉は、露通と共にそのまま大垣に着き、元大垣藩士の武士で、 もう隠居している門人「如行(じょこう)」の家に温かく迎えられます。 旅のゴールは、美濃国(岐阜県)の「大垣」です。 ついに、芭蕉が旅の終着地に着くという知らせをうけとった、蕉風グループの多くの 門人たちは、喜び勇んで美濃国(岐阜県)大垣に迎えに行きました。 敦賀の港には、まず「露通(ろつう)」が迎えに来ていました。 露通は、この『奥の細道』の旅の道連れ候補だった人なのです。 彼は、素晴らしい俳句を作る人なんですけど、めっちゃいい加減な性格をしていたのです。 それで、彼にはマネージャー役はとても務まらないだろうということで、 しっかり者の曾良に決まったのでした。 その曾良は、この旅の途中、山中温泉で腹痛のため衰弱してしまい、芭蕉と別れて療養するために 伊勢に向かいました。芭蕉の足手まといになってはいけないので、伊勢の縁者の所へ行って ゆっくり体を治すことにしたのです。 曾良と別れるとき、芭蕉はすっかり落ち込んで心細い思いをしたようですよ。 |
||||||||
| 芭蕉がとうとうゴールすると聞いた「曾良」は、伊勢から大垣へやって来て、待っていたのでした。 さらに、門人の「越人(えつじん)」も、馬を走らせて会いに来ました。 次々とお祝いに門人たちが駆けつけます。 芭蕉は、そのときの様子を、「まるで生き返った人間でもあるかのように」、 みんな再会を喜んでくれたと記しています。 このときの様子から、蕉風グループの温かさと団結力が、伝わります。 |
||||||||
| 大垣で数日過ごすと、芭蕉は、もう次の旅に出ます。 10日に行われる伊勢神宮の遷座式に間に合うようにと、9月6日、再び舟に乗ったのでした。 そして、ここで、この旅の最後の一句(結句)を詠みます。 この結句は ≪西行≫ の和歌を意識して作ったのではないかと伝わっています。 |
||||||||
| 今ぞ知る 二見の浦の はまぐりを 貝をあはせて おほふなりけり ≪西行≫ | ||||||||
 |
||||||||
| 蛤の ふたみにわかれ 行秋ぞ ≪奥の細道 最後の句 ≫ |
||||||||
| 伊勢のハマグリの「ふた」と「み」がなかなか切り離せないような、 離れがたい思いを振り切って、私はこの懐かしい人々に別れを告げ、 二見浦のほうに向かって、新たな旅の一歩を踏み出します。 秋が行き、冬に向かうこの時節に。 |
||||||||
| ハマグリの「蓋と身」向かう伊勢の「二見ヶ浦」(地名)を掛けています。 あとは、この結句の「行秋ぞ(ゆく秋ぞ)」と、旅の始めの旅立ちの句「行春や(ゆく春や)」を 呼応させています。春に旅立ち、秋に旅が終わったと、強調させているのだそうです。 |
||||||||
行春や 鳥啼魚の 目は泪 ≪ 旅立ちの句 ≫ |
||||||||
| 『奥の細道』の最後の地・大垣に、芭蕉は15日間ほど滞在したようです。 そこでたくさんの門人たちに祝福され、また、次の旅に出たのでした。 奥州路の旅は終わりましたが、これからも芭蕉の「旅を住処(すみか)」とする日々は、続きます。 |
||||||||